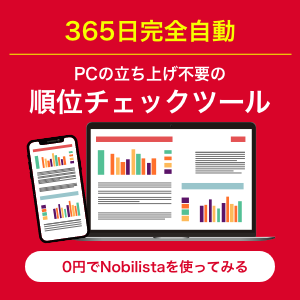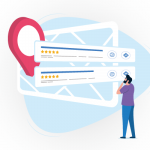AI
更新日2025年12月08日
公開日2025年10月16日
ゼロクリック検索時代トラフィック激減を乗り越えAIに選ばれる新戦略LLMO
2025年、検索の世界はついに「クリックを前提としない時代」へと突入しました。
ユーザーが検索結果ページ上で答えを得て、サイトを訪れない「ゼロクリック検索」は、GoogleのAI Overview(AI概要表示)の登場によって全体の60%を超えるまでに拡大。
その結果、多くのWebサイトが深刻なトラフィック減少という現実に直面しています。
しかし、これは単なる危機ではありません。
むしろ、SEOの新たな進化が始まったことを意味します。
本記事では、ゼロクリック検索の最新動向と、それがビジネスに与える影響をデータに基づいて徹底分析します。
さらに、従来の「強調スニペット」獲得などの対策に加え、AIに引用されることを前提とした新時代のSEO戦略。
「GEO(生成エンジン最適化)」および「LLMO(大規模言語モデル最適化)」について、実践的な手法を交えながら解説します。
検索の主役がクリックから生成AIへと移りゆく中で、あなたのサイトをAIに選ばれる存在へと進化させるための戦略を、ここで明らかにしていきます。
ゼロクリック検索とは何か?
ゼロクリック検索とは、ユーザーが検索エンジンで行った検索に対し、検索結果ページ(SERP)上で直接的な回答や情報が得られることで、どのウェブサイトのリンクもクリックすることなく検索行動が完了してしまう現象を指します。
従来、検索エンジンは情報への「入口」として機能していましたが、現在では「目的地」そのものへと変化しつつあります。
ゼロクリック検索を加速させる仕組み
この現象は、Googleがユーザー体験の向上を目指して実装してきた様々な機能によって引き起こされています。
特に以下の機能は、ゼロクリック検索の主要な要因となっています。
強調スニペット
ユーザーの質問に対する直接的な答えを、検索結果の最上部に目立つ形で表示します。
ナレッジパネル
企業、人物、場所などに関する構造化された情報を、検索結果の右側(モバイルでは上部)にカード形式で表示します。
AI Overview(AI概要)
2025年以降、最も大きな影響を与えている機能です。
生成AIがウェブ上の情報を要約し、検索結果の最上部に包括的な回答を提示します。
これにより、ユーザーは複数のサイトを閲覧する手間なく、複雑な質問に対する答えを得られるようになりました。
なぜ今、ゼロクリック検索が急増しているのか
ゼロクリック検索の急増は、単一の要因ではなく、技術の進化とユーザー行動の変化が複雑に絡み合った結果です。
AIと機械学習技術の飛躍的な進歩により、検索エンジンはユーザーの入力したキーワードの裏にある「検索意図」をより深く、正確に理解できるようになりました。
その結果、単にキーワードに一致するページを提示するのではなく、ユーザーが本当に求めている「答え」そのものを直接提供することが可能になったのです。
また、スマートフォンの普及によるモバイルファーストへの移行と、スマートスピーカーの登場による音声検索の一般化も、この流れを加速させています。
小さな画面で効率的に情報を得たい、あるいは画面を見ずに音声だけで答えを知りたいといったユーザーのニーズが、検索エンジンの「回答エンジン」化を後押ししているのです。
衝撃的なデータ!ゼロクリック検索の現状
ゼロクリック検索の増加は、感覚的なものではなく、具体的なデータによって裏付けられています。
近年のゼロクリック検索率の推移は、ウェブサイト運営者にとって看過できない状況を示しています。
| 年 | ゼロクリック検索率 | 主な出来事 |
| 2019年 | 約50% | 強調スニペットの普及が進む |
| 2022年 | 約55% | モバイル検索の比率がさらに高まる |
| 2025年 | 60%以上 | GoogleによるAI Overviewの本格導入 |
この影響は、実ビジネスの世界で深刻な結果をもたらしています。
例えば、マーケティングソフトウェア大手のHubSpotは、AI検索の台頭により、自社ブログへのオーガニック検索流入が最大で80%も減少したと報告しており、この問題の深刻さを物語っています。
ゼロクリック検索がSEOとビジネスに与える壊滅的な影響
ゼロクリック検索の増加は、単にウェブサイトへの訪問者が減るというだけでなく、従来のデジタルマーケティングの前提を根底から覆す、構造的な変化をもたらしています。
オーガニックトラフィックの激減
最も直接的で深刻な影響は、オーガニック検索からのトラフィック減少です。
マーケティング会社Seer Interactiveの調査によると、Googleの検索結果にAI概要が表示された場合、ウェブサイトへのオーガニッククリック率は、わずか1年で1.41%から0.64%へと半減以下に低下しました。
これは、これまで検索順位1位を獲得するために多大な労力を費やしてきた多くの企業にとって、その努力が報われにくくなっていることを意味します。
特にEC業界ではこの問題は「Google Zero」と呼ばれ、危機感を募らせています。
Adobe Analyticsの調査では、2025年のAmazonプライムデーにおいて、生成AIを情報源としたECサイトへのトラフィックが前年比で3300%も増加したと報告されており、消費者がGoogle検索を介さずに直接商品比較や購買検討を行う流れが加速していることを示しています。
従来のビジネスモデルの崩壊
トラフィックの減少は、ページビュー(PV)に依存するビジネスモデル、特に広告収益を主とするメディアサイトに壊滅的な打撃を与えます。
訪問者がサイトを訪れなければ、広告が表示される機会そのものが失われ、収益は直接的に減少します。
また、サイトへの訪問は、ブランド認知を形成し、顧客との関係を構築する重要な機会でした。
ゼロクリック検索は、この貴重な顧客接点を奪い、ユーザーの記憶にブランドが残る機会を減少させます。
結果として、リード獲得や見込み客育成といった、コンテンツマーケティングが担ってきた重要な機能が麻痺してしまう危険性があります。
SEOの評価指標が変わる
トラフィックという従来のゴールが揺らぐ今、SEOの成功を測るための指標(KPI)も大きく変化させる必要があります。
もはや、検索順位やクリック率(CTR)だけを追い求めても、ビジネス成果には結びつきません。
| 従来の主要指標 | ゼロクリック時代の新指標 | なぜ重要か |
| 検索順位 | AI回答での引用率・表示率 | AIに引用されることが新たな「1位」となるため |
| クリック率 (CTR) | ブランド言及率・知名度 | クリックされずとも、ブランド名が認知されることが重要になるため |
| セッション数 | ブランド指名検索数 | ユーザーが直接ブランド名で検索する行動は、高い関心の証であるため |
| コンバージョン数 | チャネル横断での貢献度 | SEOが直接的なCVだけでなく、他チャネルのCVにどう貢献したかを測る必要があるため |
これからのSEOは、単独のチャネルとして完結するのではなく、AIや他のマーケティングチャネルと連携し、ビジネス全体の目標にどう貢献するかという、より統合的な視点が求められます。
ゼロクリック検索時代の新SEO戦略
この厳しい環境を生き抜くためには、戦略の転換が不可欠です。
それは、従来のSEOを捨て去るのではなく、新しい現実に合わせて進化させることを意味します。戦略は大きく「防御的戦略」と「攻撃的戦略」の二つに分けられます。
防御的戦略 検索結果での露出を最大化する
まずは守りを固め、クリックされる可能性が残る領域で、最大限の露出を確保するための施策です。
強調スニペット獲得の徹底攻略
強調スニペットは、ゼロクリック検索の要因であると同時に、クリックを獲得するための最大のチャンスでもあります。
以下の4つのタイプ別に最適化を進めましょう。
段落形式
「〜とは」といった定義を問う質問に対し、50〜60文字程度の簡潔な回答を記事の冒頭に記述します。
リスト形式
「〜の方法」といった手順を示す検索に対し、HTMLの順序付きリスト(<ol>)や順序なしリスト(<ul>)タグを適切に使い、コンテンツを構造化します。
表形式
「〜の比較」といった検索に対し、HTMLの<table>タグを用いて情報を整理し、比較が容易な形で提示します。
動画形式
「〜のやり方」といった実演を求める検索に対し、YouTube動画のタイトルや説明文、テロップにキーワードを盛り込み、動画の構造化データを実装します。
構造化データの高度な活用
AIがコンテンツの内容を正確に理解し、検索結果で豊かに表示(リッチリザルト)させるために、構造化データの実装は不可欠です。特に以下のスキーマは重要です。
FAQスキーマ
よくある質問とその回答をマークアップすることで、検索結果にアコーディオン形式で表示される可能性が高まります。
How-toスキーマ
手順を説明するコンテンツに実装することで、ステップ・バイ・ステップ形式での表示が期待できます。
これらの実装は、JSON-LD形式で行うことがGoogleによって推奨されており、AIにとって最も解釈しやすい方法です。
攻撃的戦略 AIに選ばれ、引用されるコンテンツを作る (GEO/LLMO)
守りを固めるだけでは不十分です。
これからは、積極的にAIに「選ばれ」「引用される」ための、全く新しい最適化が求められます。
それがGEO(Generative Engine Optimization)やLLMO(Large Language Model Optimization)と呼ばれる考え方です。
GEO/LLMOとは、従来の検索エンジンランキングを対象とするSEOとは異なり、AIが回答を生成するプロセスそのものを対象とし、自社の情報がその回答ソースとして引用されることを目指す一連の最適化活動を指します。
AIに引用されるコンテンツには、共通する3つの要素があります。
1.一次情報と独自性
AIは既存の情報を学習し要約することは得意ですが、新しい情報を自ら生み出すことはできません。
独自の調査データ、顧客へのインタビュー、専門家としての深い洞察など、自社でしか提供できない一次情報こそが、AIにとって価値ある情報源となります。
2.権威性(E-E-A-T)
Googleが重視するE-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)は、AIが情報源の信頼性を評価する上でも重要な指標となります。
誰がその情報を発信しているのか(著者情報)、その組織は信頼できるのか(運営者情報)を明確にすることが、これまで以上に重要です。
3.明瞭性
AIがコンテンツを正確に解釈できるよう、論理的で分かりやすい文章構造を心がける必要があります。
見出しを適切に使い、専門用語は丁寧に解説し、結論を先に述べるなどの工夫が求められます。
海外企業の先進事例に学ぶ
すでに海外の先進企業は、この新しい現実に対応するための戦略を実践しています。
Batteries Plus(バッテリー通販)
AIが自社について言及した際、その引用元となっている情報源(Wikipedia、業界団体、レビューサイトなど)を徹底的に精査し、情報が正確かつ最新であるように管理しています。
これは、AIが参照するであろう外部の情報をコントロールするという、地道かつ効果的な戦略です。
Kendra Scott(ジュエリーブランド)
AIによる検索を意識し、特定のテーマやコンセプトに沿った商品をまとめたページを、AIプラットフォームを活用して1年間で8,000ページも追加しました。
これにより、年間ウェブトラフィックの5%をAI経由で獲得することに成功しています。
多チャネル戦略への転換
ゼロクリック検索の増加は、私たちに「SEO一本足打法」の危険性を突きつけています。
Googleという単一のプラットフォームに集客を依存するビジネスモデルは、アルゴリズムの変更一つで揺らぐ、極めて脆弱なものなのです。
ブランド指名検索を増やす
これからの時代、最も安定したトラフィックソースは「ブランド指名検索」です。
ユーザーが能動的にあなたの会社名やサービス名で検索してくれる状態を作り出すことが、究極のSEO対策と言えるでしょう。
そのためには、検索エンジンの外での活動が不可欠です。
X(旧Twitter)やLinkedInなどのSNSで専門知識を発信したり、ユーザーコミュニティを運営したりすることで、潜在顧客との関係を構築し、ファンを育てることが重要になります。
顧客と直接繋がる
プラットフォームに依存せず、自社でコントロール可能なチャネルを持つことの価値が、今、再評価されています。
メールマガジンを通じて定期的に有益な情報を届けたり、ウェビナーを開催して顧客と直接対話したりすることで、アルゴリズムの気まぐれに左右されない、強固な顧客基盤を築くことができます。
まとめ
ゼロクリック検索の時代は、多くのウェブサイト運営者にとって厳しい試練の時です。
しかし、それは「SEOの終わり」を意味するものではなく、「新しいルールの始まり」を告げるゴングに他なりません。
これからのSEOでは、「クリック」を求めるのではなく、AIに「引用」され、ユーザーから「信頼」されることが新たなゴールとなります。
そのためには、強調スニペット対策や構造化データといった「防御」の施策で足場を固めつつ、GEO/LLMOという「攻撃」の施策で積極的にAIに働きかける、攻守両面の戦略が不可欠です。
そして最も重要なのは、SEOという枠組みだけに囚われず、SNS、メール、コミュニティなど、多角的なチャネルを通じてユーザーと直接的な関係を築く「ブランド構築」の視点を持つことです。
それこそが、変化の激しいAI時代を生き抜き、選ばれ続けるウェブサイトになるための、唯一の道と言えるでしょう。